Market Data
--------------------------------------------
【日経平均】
34267円54銭(△285円18銭=0.84%)
--------------------------------------------
【TOPIX】
2513.35(△24.84=1.00%)
--------------------------------------------
【グロース250】
640.87(△6.95=1.10%)
--------------------------------------------
【プライム売買高】15億8398万株(▲1億0576万株)
--------------------------------------------
【売買代金】3兆5147億円(▲3644億円)
--------------------------------------------
【値上がり銘柄数】799(前日:1322)
【値下がり銘柄数】762(前日:276)
--------------------------------------------
【新高値銘柄数】53(前日:72)
【新安値銘柄数】4(前日:5)
--------------------------------------------
【25日騰落レシオ】91.35(前日:89.94)
--------------------------------------------
■本日のポイント
1.日経平均は285円高と続伸、朝方には一時400円を超す上昇
2.前日のNYダウは312ドル高、米相互関税の一部見直しを評価
3.米自動車関税への救済策に対する期待も膨らみ自動車株が買われる
4.トヨタやホンダ、スズキが高く、デンソーやブリヂストンも堅調
5.ディスコやアドテストが安く、ニトリHDやフジHDも値を下げる
日経平均は続伸。きのうと似た動きで、米国要因で高く始まった後の上値は重かった。先週に4桁の上げ下げを繰り返しただけに株価の急変動に対する懸念が拭いきれない状況ではあるが、場中の動きがさえないと底打ち感が高まってこない。
きょうは自動車関連に買いが入ったが、きのうの上昇をけん引した半導体株は軟調であった。逆にきのう弱かった防衛関連は買われている。
物色が日替わりとなっている上に、チャートを見ると、これらのいずれも底値圏を脱したとまでは言えない。何か相場の核となるような銘柄および業種・テーマが出てきてほしいところだ。あすはオランダのASMLホールディング、17日にはディスコと台湾のTSMCが決算を発表予定で、目先は半導体株の刺激材料が多い。半導体株が再び日本株の主役になれるか、この先の動向が注目されるだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
37272.03 均衡表雲上限(週足)
37211.13 13週移動平均線
36482.53 均衡表雲下限(週足)
36293.42 ボリンジャー:-1σ(26週)
35770.20 25日移動平均線
35617.56 新値三本足陽転値
35595.49 均衡表基準線(週足)
35150.65 均衡表転換線(週足)
35142.92 ボリンジャー:-1σ(13週)
34531.90 ボリンジャー:-2σ(26週)
34506.72 均衡表基準線(日足)
34267.54 ★日経平均株価15日終値
33770.37 ボリンジャー:-1σ(25日)
33528.52 6日移動平均線
33074.70 ボリンジャー:-2σ(13週)
32918.74 均衡表転換線(日足)
32770.37 ボリンジャー:-3σ(26週)
31770.54 ボリンジャー:-2σ(25日)
31006.49 ボリンジャー:-3σ(13週)
29770.72 ボリンジャー:-3σ(25日)
ローソク足は3本連続で小陰線を引いたが、上向きの5日移動平均線を割り込むことなく推移。ザラ場高値と安値も前日から切り上がり株価の反騰トレンドを確認する形となった。一方、下降中の25日線との下方乖離率は4.20%に縮小しており、リバウンド圧力の低下も推察される。三役逆転下にある一目均衡表では、転換線が下降を続けていることもあり、足元の値戻しがダマシに終わるリスクへの留意も必要となろう。
【大引け概況】
15日の日経平均株価は続伸し、終値は前日比285円18銭高の3万4267円54銭だった。
本日のマーケット動画
時間:00:01:25 容量:17.96M ▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら

前日の米株式市場では、NYダウは312ドル高と上昇した。トランプ米政権がスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税の対象から一時除外したことを好感する買いが流入した。これを受け、東京株式市場も日経平均株価は上昇してスタートし、午前9時30分過ぎには400円を超える値上がりとなる場面があった。トランプ米大統領が14日、「一部の自動車メーカーを助ける何らかの方策を検討している」と語ったと伝わり、自動車関税の救済策への期待が高まり自動車株が買われた。米株式市場でフォード・モーターなど自動車株が上昇した流れを受け、東京株式市場でもトヨタやホンダ、SUBARU、デンソーなど自動車や部品銘柄に買いが集まった。東証の業種別騰落率ランキングで輸送用機器は値上がり率首位となった。
後場に入ってからは3万4300円前後を中心とする一進一退が続いた。赤沢亮正経済財政・再生相が16日から訪米して、ベッセント米財務長官と日米関税交渉に臨むのを前に、積極的な売買を手控える動きも強まった。為替が一時1ドル=142円80銭台とやや円高方向に振れたことも相場の上値を抑えた。米国側から関税引き下げの代わりに円安是正を求められるとの思惑は根強く、投機筋が円相場の先高観を強めている。
中谷元防衛相が15日の閣議後記者会見で2025年度の防衛関連予算の合計が22年度国内総生産(GDP)比で上昇したと発表したことから、防衛関連産業の受注増につながるとの思惑で三菱重など防衛関連銘柄も上昇した。国内長期金利の上昇を受けて、利ざや改善期待から三菱UFJなどの銀行株も買われた。
日経平均は続伸したものの、前日に続き上値の重さが気になるところだ。3月26日の直近高値(3万8220円)から4月7日の安値(3万0792円)までの下げ幅(7428円)の半値戻しである34506円が壁になっているようだ。この水準を早期にクリアしてくるかが、目先の焦点になりそうである。日米の関税交渉が17日から始まるだけに協議内容が気がかりなほか、トランプ大統領の関税に関する発言次第では再び波乱含みの展開となる可能性も捨てきれないだけに、引き続き積極的な売り買いは手控えられ、省エネ相場が続きそうだ。

業種別株価指数(33業種)は輸送用機器、ゴム製品、銀行業などが上昇。電気・ガス業、陸運業、不動産業などは下落した。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。終値は24.84ポイント(1.00%)高の2513.35だった。JPXプライム150指数は続伸し、11.94ポイント(1.10%)高の1102.22で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆5147億円と、1月21日以来2カ月半ぶりの低水準だった。売買高は15億8398万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は799。値下がりは762、横ばいは76だった。
個別銘柄では、住友電工、フジクラなど電線株が買われたほか、川崎重工業や三菱重工業が高く、トランプ大統領が自動車メーカーの支援を検討と発表したことでトヨタ自動車、スズキ、マツダ、ホンダ、SUBARU、三菱自など自動車株の上げも目立った。デンソーやブリヂストンも値を上げた。三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループが上昇し、東京エレクトロンやソフトバンクグループ、ソニーグループもしっかり。このほか、横河電機、HOYA、などが買われた。
半面、今期純利益見通しが14%減と発表した東宝が売られたほか、三越伊勢丹HD、ニトリホールディングスなど小売株の一部も弱い。ディスコやアドバンテスト、レーザーテックが安く、ディー・エヌ・エーや任天堂、SMCが軟調。ニトリホールディングスやフジ・メディア・ホールディングスが値を下げ、アシックスが売られた。このほか、資生堂、東急、東急不動産HD、東京建物、レーザーテック、JR西日本などが売られた。
東証スタンダード市場は米関税政策に対する過度な不安が和らぎ、投資家心理が改善し買いが優勢となった。
スタンダードTOP20は小幅続伸。出来高4億2582万株。
値上がり銘柄数887、値下がり銘柄数521と、値上がりが優勢だった。
個別ではTHE WHY HOW DO COMPANYがストップ高。三井住建道路、鳥越製粉、東洋精糖、北浜キャピタルパートナーズ、きょくとうなど44銘柄は年初来高値を更新。ラピーヌ、フレンドリー、ウッドフレンズ、エディア、テイツーが買われた。
一方、MS&Consulting、マックハウス、植松商会が年初来安値を更新。インターライフホールディングス、セラク、テンダ、東名、ウィルソン・ラーニング ワールドワイドが売られた。
東証グロース市場は前日の米株式相場の上昇などを支えに投資家心理が改善し、新興市場でも買いが優勢だった。グロースの主力株の一角や好決算を発表した銘柄の上昇も目立った。
米政権による高関税政策の一部に軌道修正の動きが見られ、前日の米主要株価指数はそろって続伸した。米株市場の上昇を受け新興市場でも投資家の過度な不安心理がやや後退し、グロース250は一時前日比2%以上上昇した。
市場関係者は「新興市場は関税影響を受けにくく、心理さえ改善すれば買いは入りやすい」と分析。個別の買い材料を手掛かりに主力株の一角に買いが集まった。
東証グロース市場250指数は4日続伸した。終値は前日比6.95ポイント(1.10%)高の640.87だった。グロースCoreは反発。
グロース市場ではABEJA、トライアルが上昇した。一方、クオリプス、ベースフードが下落した。
値上がり銘柄数339、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。
個別では、VRAIN Solution、フライヤー、エコモット、プロディライトがストップ高。オルツ、イメージ情報開発、キッズウェル・バイオ、ABEJA、TWOSTONE&Sonsは一時ストップ高と値を飛ばした。Cocolive、MFS、ククレブ・アドバイザーズ、Synspective、イントランスなど23銘柄は年初来高値を更新。日本ナレッジ、ライズ・コンサルティング・グループ、ワンダープラネット、バリュークリエーション、WACULが買われた。
一方、Globeeが一時ストップ安と急落した。ロゴスホールディングスは年初来安値を更新。ソーシャルワイヤー、マテリアルグループ、ベースフード、GRCS、GLOEが売られた。
15日午前の日経平均株価は続伸し、午前終値は前日比302円66銭高の3万4285円02銭だった。
前日の米株式市場では、NYダウは312ドル高と上昇した。トランプ米政権がスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税の対象から一時除外したことを好感する買いが流入した。米株高を受け、東京株式市場も日経平均株価は上昇してスタートし、400円を超える値上がりとなる場面があった。特にトランプ米大統領が14日、「一部の自動車メーカーを助ける何らかの方策を検討している」と語ったと伝わり、自動車関税の救済策への期待が高まり自動車株が買われた。
米株式市場でフォード・モーターなど自動車株が上昇した流れを受け、東京株式市場でもトヨタやホンダ、マツダ、デンソーなど自動車や部品銘柄に買いが集まった。大手重工や銀行株なども高い。東証の業種別騰落率ランキングで輸送用機器は値上がり率首位となった。
買い一巡後は伸び悩む場面もみられた。赤沢亮正経済再生担当相は16日から訪米し、ベッセント米財務長官と関税交渉に臨む予定だ。関税引き下げ交渉に関し、米国側から円安是正を求められるとの思惑も根強く、日本株の上値を抑えた。
前場のプライム市場の売買代金は1.6兆円に留まっており、先週の乱高下の余韻はほぼ無くなったと言えよう。一方、投資家心理を示唆する日経平均VIは低下傾向にあるが、まだ34ポイント台で推移している。米VIX指数も30ポイント台で推移していることから、日米のボラティリティが低下するにはもう少し時間はかかりそうだ。
市場は、朝令暮改の米国関税方針に慣れ始めているが、ボラティリティが高い状況下、腰の据わった長期資金の流入は期待しにくい。市場が落ち着きを取り戻したと言われる水準(米VIX指数が20ポイント台前後、日経平均VIが25ポイント前後)までそれぞれ低下しないことには、投資家は静観を選択するだろう。後場の東京株式市場も薄商いで、日経平均は34200円水準でのもみ合いとなろう。
 東証株価指数(TOPIX)は続伸した。前引けは27.59ポイント(1.11%)高の2516.10だった。JPXプライム150指数は続伸し、13.09ポイント(1.20%)高の1103.37で前場を終えた。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。前引けは27.59ポイント(1.11%)高の2516.10だった。JPXプライム150指数は続伸し、13.09ポイント(1.20%)高の1103.37で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆6703億円、売買高は7億3777万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は975。値下がりは585、横ばいは76だった。
業種別では、輸送用機器、ゴム製品、非鉄金属、銀行、精密機器などが上昇した一方、電気・ガス、空運、不動産、陸運、水産・農林などが売られた。
個別銘柄では、三菱重工業や川崎重工業が高く、三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループが値を上げた。住友電工、フジクラなど電線株が買われたほか、トランプ大統領が自動車メーカーの支援を検討と発表したことでトヨタ自動車、スズキ、マツダ、ホンダ、SUBARU、三菱自など自動車株の上げも目立った。このほか、デンソー、横河電機、HOYAなどが買われた。
一方、今期純利益見通しが14%減と発表した東宝が売られたほか、J.フロント リテイリング、三越伊勢丹など百貨店株も弱い。このほか、資生堂、東急、東急不HD、東京建物、レーザーテック、JR西などが売られた。ディスコやアドバンテストが軟調。ニトリホールディングスやフジ・メディア・ホールディングス、SMCが値を下げた。
東証スタンダード市場は前日の米国株上昇を受けて投資家心理が上向き、買いが優勢になった。
スタンダードTOP20は続伸。出来高2億2467万株。
値上がり銘柄数927、値下がり銘柄数427と、値上がりが優勢だった。
個別ではTHE WHY HOW DO COMPANYが一時ストップ高と値を飛ばした。鳥越製粉、東洋精糖、北海道コカ・コーラボトリング、一正蒲鉾、サトウ食品など28銘柄は年初来高値を更新。フレンドリー、川本産業、ウッドフレンズ、ジェイ・エスコムホールディングス、ラピーヌが買われた。
一方、MS&Consultingが年初来安値を更新。セラク、インターライフホールディングス、テンダ、東名、ウィルソン・ラーニング ワールドワイドが売られた。
東証グロース市場は前日の米株式相場の上昇が支えになった。15日の日経平均株価も上昇して投資家心理がやや改善したことで、グロース市場でもトライアルなど主力株に買いが入った。
東証グロース市場250指数は続伸した。前引けは前日比7.68ポイント(1.21%)高の641.60だった。グロースCoreも反発。
グロース市場ではサンバイオ、Synsも上昇した。一方、クオリプス、ベースフードは下落した。
値上がり銘柄数366、値下がり銘柄数189と、値上がりが優勢だった。
個別では、VRAIN Solution、キッズウェル・バイオがストップ高。イメージ情報開発、ABEJA、TWOSTONE&Sonsは一時ストップ高と値を飛ばした。Cocolive、MFS、ククレブ・アドバイザーズ、Synspective、イントランスなど20銘柄は年初来高値を更新。エコモット、夢展望、ジェイフロンティア、オルツ、WACULが買われた。
一方、Globeeが一時ストップ安と急落した。ロゴスホールディングス、マーキュリー、マテリアルグループ、GRCS、ベースフードが売られた。
【寄り付き概況】
15日の日経平均株価は続伸で始まった。始値は前日比366円65銭高の3万4349円01銭。
前日の米株式市場では、NYダウは312ドル高と上昇。トランプ米政権がスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税の対象から外したことを好感する買いが流入した。これを受け、日経平均株価も値を上げてスタートした。為替は1ドル=143円20銭前後と前日夕方に比べやや円安で推移している。
米自動車株が上昇した流れを受け、トヨタやホンダ、マツダに買いが波及している。トヨタは買い気配で始まったあと、5%強の上昇となった。
東証株価指数(TOPIX)は続伸している。
個別では、ファストリやソフトバンクグループ(SBG)、ソニーGが上昇している。一方、TDKや資生堂、ディスコが下落している。
「需給」
「主要3指数は揃って続伸」
週明けのNY株式市場は主要3指数は揃って続伸。
スマートフォンやコンピューターが相互関税の対象から除外されたことを受けた格好。
ただ、今後の関税を巡る不透明感から3指数はいずれも日中高値から押し戻された。
アップルが2.2%高、デルが4%高、HPが2.5%高。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は0.3%と小幅な上昇。
エヌビディアは0.2%下落。
VIX(恐怖)指数30.89と終値ベースで4月3日以来の低水準。
決算が好調だったゴールドマン・サックスは1.9%上昇。
3月のNY連銀消費者調査で1年先のインフレ期待は3.6%。
2月の3.1%から上昇し2023年10月以来の高水準。
3年先インフレ期待は3%と変わらず。
5年先のインフレ期待は2.9%と前月の3%からわずかに低下した。
債券市場は落ち着きを取り戻した格好で国債利回りは低下。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.531%とやや拡大。
10年国債利回りは4.383%。
5年国債利回りは4.018%
2年国債利回りは3.853%。
ドル円は143円を挟んだ展開。
WTI原油先物5月限は0.03ドル(0.05%)高の1バレル=61.53ドル。
金先物6月限は前日比18.30ドル(0.56%)安の1オンス=3226.30ドル。
SKEW指数は127.54?128.64?135.71。
恐怖と欲望指数は12?19。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
3月11日が14。
4月8日が3。
週明けのNYダウは312ドル(0.78%)高の40524ドルと続伸。
高値40778ドル、安値40159ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは101.97(前日95.31)。
NASDAQは107ポイント(0.64%)高の16831ポイントと続伸。
高値17136ポイント、安値16661ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは84.56(前日78.30)。
S&P500は42ポイント(0.79%)高の5405ポイントと続伸。
高値5459ポイント、安値5358ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは99.02(前日91.98)。
週明けのダウ輸送株指数は163ポイント(1.22%)高の13573ポイントと続伸。
SOX指数は12ポイント(0.31%)高の4003ポイントと続伸。
VIX指数は30.89(前日37.56)。
NYSEの売買高は12.38億株(前日13.48億株)。。
3市場の合算売買高は182億株(前日191.9億株、過去20日平均182億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の34295円。
ドル建ては大証日中比240円高の34410円。
ドル円は142.98円。
10年国債利回り4.383%。
2年国債利回りは3.853%。
「25日線35880円、4月SQ値32737円」
週明けの日経平均は寄り付き421円高。
終値は396円(△1.18%)高の33982円と反発。
高値34325円。
安値33887円。
2日連続で日足陰線。
SQ値32737円に対しては2勝0敗。
ただ先週金曜日の下落幅1023円に対して38.7%の戻り。
3月27日は37873円?37859円にマド。
3月28日は37556円?37359円にマドで下に2空。
3月31日は36864円?36440円にマドで下に3空。
4月3日は35426円?35044円にマド。
4月7日は33259円?33158円にマド。
日経平均は35日連続で一目均衡の雲の下。
上限は38551円。
下限は37865円。
TOPIXは21ポイント(△0.88%)高の2488ポイントと反発。
25日線(2646ポイント)を11日連続で下回った。
75日線(2708ポイント)を11日連続で下回った。
200日線(2704ポイント)を11日連続で下回った。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は11.13ポイント(△0.88%)高の1280.70ポイントと反発。
東証グロース250指数は2.52ポイント(△0.40%)高の633.92と3日続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲0.82%(前日▲1.19%)。
プライム市場の売買代金は3兆8782億円(前日5兆4413億円)。
売買高は16.89億株(前日24.35億株)。
値上がり1322銘柄(前日501銘柄)。
値下がり276銘柄(前日1100銘柄)。
新高値72銘柄(前日42銘柄)。
新安値5銘柄(前日23銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは89.94(前日82.46)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.51(前日81.62)。
NTレシオは13.66倍(前日13.61倍)。
4月1日が13.38倍
20年12月30日が12.90。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは4勝8敗で33.33%。
東証グロース市場指数4勝8敗で33.33%。
下向きの25日線(35880円)から▲5.29%(前日▲6.70%)。
12日連続で下回った。
下向きの75日線は37901円。
36日連続で下回った。
下向きの200日線(38292円)から▲11.26%(前日▲12.34%)。
34日連続で下回った。
下向きの5日線は38292円。
3日連続で上回った。
13週線は37189円。
26週線は38043円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.454%(前日▲17.789%)。
買い方▲13.352%(前日▲14.020%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.114%(前日▲6.339%)。
買い方▲16.819%(前日▲17.581%)。
空売り比率は40.9%(前日41.7%、4日連続で40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.7%(前日11.6%)。
2日ぶりに2ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
昨年12月26日が14.4%。
日経VIは38.92(前日44.36)。
日経平均採用銘柄のPERは13.62倍(前日13.51倍)。
前期基準では14.65倍。
EPSは2495円(前日2485円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.25倍(前日1.24倍)。
BPSは27185円(前日27065円)。
日経平均の予想益回りは7.34%。
予想配当り利回りは2.33%。
指数ベースではPERは17.28倍(前日17.09倍)。
EPSは1966円(前日1965円)。
PBRは1.65倍(前日1.63倍)。
BPSは20595円(前日20604円)。
10年国債利回りは1.335%(前日1.270%)。
プライム市場の予想PERは13.63倍。
前期基準では14.68倍。
PBRは1.20倍。
プライム市場の予想益回りは7.33%。
配当利回り加重平均は2.66%。
東証プライムのEPSは181.72(前日181.36)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は29.2%(前日29.3%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は28円高の2476円(前日は2448円)。
プライム市場の売買単価は2295円(前日2234円)。
プライム市場の時価総額864兆円(前日856兆円)。
ドル建て日経平均は238.69(前日233.20)と反発。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の34295円。
高値34505円、安値33815円。
週明けの大証夜間取引終値は日中比130円高の34300円。
気学では火曜は「大下放れすると底入れをみることあり注意」。
水曜は「初め高いと後安の日。吹き値あれば売り狙え」。
木曜は「押し目買い方針の日」。
金曜は「相場の居所が安値にある時は急伸する」。
ボリンジャーのプラス1σが37870円。
プラス2σが39860円。
マイナス1σが33890円。
マイナス2σが31900円。
マイナス3σが299105円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39209円。
プラス2σが41941円。
マイナス1σが35088円。
マイナス2σが32958円。
マイナス3σが30887円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には今年唯一の「全惑星順行(?5月4日)」。
《今日のポイント4月15日》
(1)週明けのNY株式市場は主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは4.383%。
5年国債利回りは4.018%
2年国債利回りは3.853%。
ドル円は143円を挟んだ展開。
SKEW指数は127.54?128.64?135.71。
恐怖と欲望指数は12?19。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
3月11日が14。
4月8日が3。
(2)週明けのダウ輸送株指数は163ポイント(1.22%)高の13573ポイントと続伸。
SOX指数は12ポイント(0.31%)高の4003ポイントと続伸。
VIX指数は30.89(前日37.56)。
NYSEの売買高は12.38億株(前日13.48億株)。。
3市場の合算売買高は182億株(前日191.9億株、過去20日平均182億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の34295円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆8782億円(前日5兆4413億円)。
売買高は16.89億株(前日24.35億株)。
値上がり1322銘柄(前日501銘柄)。
値下がり276銘柄(前日1100銘柄)。
新高値72銘柄(前日42銘柄)。
新安値5銘柄(前日23銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは89.94(前日82.46)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.51(前日81.62)。
NTレシオは13.66倍(前日13.61倍)。
4月1日が13.38倍
20年12月30日が12.90。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)下向きの25日線(35880円)から▲5.29%(前日▲6.70%)。
12日連続で下回った。
下向きの75日線は37901円。
36日連続で下回った。
下向きの200日線(38292円)から▲11.26%(前日▲12.34%)。
34日連続で下回った。
下向きの5日線は38292円。
3日連続で上回った。
13週線は37189円。
26週線は38043円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.454%(前日▲17.789%)。
買い方▲13.352%(前日▲14.020%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.114%(前日▲6.339%)。
買い方▲16.819%(前日▲17.581%)。
(6)空売り比率は40.9%(前日41.7%、4日連続で40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.7%(前日11.6%)。
2日ぶりに2ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
昨年12月26日が14.4%。
日経VIは38.92(前日44.36)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは13.62倍(前日13.51倍)。
前期基準では14.65倍。
EPSは2495円(前日2485円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.25倍(前日1.24倍)。
BPSは27185円(前日27065円)。
日経平均の予想益回りは7.34%。
予想配当り利回りは2.33%。
指数ベースではPERは17.28倍(前日17.09倍)。
EPSは1966円(前日1965円)。
PBRは1.65倍(前日1.63倍)。
BPSは20595円(前日20604円)。
10年国債利回りは1.335%(前日1.270%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は29.2%(前日29.3%)。
プライム市場の単純平均は28円高の2476円(前日は2448円)。
プライム市場の時価総額864兆円(前日856兆円)。
ドル建て日経平均は238.69(前日233.20)と反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが37870円。
プラス2σが39860円。
マイナス1σが33890円。
マイナス2σが31900円。
マイナス3σが299105円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39209円。
プラス2σが41941円。
マイナス1σが35088円。
マイナス2σが32958円。
マイナス3σが30887円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には今年唯一の「全惑星順行(?5月4日)」。
今年の曜日別勝敗(4月14日まで)
?
月曜7勝6敗
火曜8勝5敗
水曜8勝6敗
木曜8勝5敗
金曜4勝10敗
電子端末から。
?
日経平均株価が週間で9%下落した4月第1週(3月31日ー4月4日)。
海外投資家は現物株を約6000億円買い越した。
「4月の海外勢の現物株買い」は株式市場でよく知られる経験則。
だが、急落週に株価指数先物ではなく、現物の「実弾売り」が大規模に出ていたとなれば、今年はこの経験則は危うくなる。
4月第1週に海外勢は現物を買い越した一方、先物を1兆3700億円売り越した。
差し引きで7700億円の売り越し。
先物だけでみると2023年10月第1週以来、およそ1年半ぶりの大きさ。
JPXの投資部門別売買動向だけをみれば、4月第1週の急落は海外勢の先物売りが主因ということになる。
例年3月末と9月末は「配当金の付け替えトレード」と呼ばれる売買が活発になる。
現物買い・先物売りの裁定持ち高を本国口座で管理している外資系証券の自己勘定。
3月と9月末の日本企業の配当権利落ち日前に東京の口座に持ち高を移すことが多い。
日本の口座で配当金を受け取った方が、税制優遇などがあるためとされる。
この過程では東京の口座に移した週には海外勢の現物売り・先物買い、証券自己の現物買い・先物売りの流れとなる。
配当落ち日後に再び本国の口座に持ち高を移す際はその逆だ。
この逆の動きとなる際に、海外勢は現物買いとなるため、4月の海外勢の現物株買いの経験則につながったとみられる。
ただ、これは相場に影響しない表面上の買い越しだ。
今年の場合、配当落ち日後に当たる4月第1週に証券自己は現物で1兆8100億円の売り越し(3月第4週は1兆3900億円の買い越し)。
一方先物は1兆4300億円の買い越し(同1兆1900億円の売り越し)だった。
海外勢の先物1兆3700億円の売り越しとほぼ同規模の買い越し。
配当金の付け替えトレードがあったことがうかがえる。
過去の3月と9月末も2主体の現先の売買規模はおおよそ同規模で逆になることが多かった。
海外勢の1兆3700億円の売り越しを「相場急落を招いた主因として捉えてはいけないのではないかという見方だ。
ただ財務省が10日発表した3月30−4月5日の対外及び対内証券売買契約などの状況。
実は4月第1週は海外勢が現物を相応の規模で売ったとの見方ができるかもしれない。
財務省の統計では海外勢は3月30ー4月5日に国内株を1兆8000億円買い越した。
1兆8000億円の買い越しは4月第1週の証券自己の現物売りとほぼ同規模。
言い換えれば、海外勢の買いとしてこの1兆8000億円がJPXのデータにでも出てくる必要がある。
となれば、現物でみた場合、財務省統計の1兆8000億円の買い越し、JPX統計の6000億円買い越しの差は1兆2000億円。
これが相場に影響する海外勢の実需フローだったとの見方もできそうだ。
その場合、4月第1週に海外勢は少なくとも1兆2000億円規模で現物株を売ったことになる。
JPXと財務省の統計には2つの大きな違いがある。
1つ目は、前者は先物の売買を含むが、後者は含まない。
2つ目は業者間の店頭取引(OTC、市場外取引)の売買を前者は含まないが、後者は含む。
期末の配当金の付け替えトレードのような特殊売買はOTCで実施されることが多いとされる。
そのため、JPXのデータにはそもそも出てこない可能性もある。
ブルームバーグ通信によると英国のマルチ戦略のヘッジファンド、アイスラー・キャピタルが、ボラティリティー(相場変動率)の上昇を受け、
同社のトレードチームが出した損失が約3000万ドル(約43億円)に膨らみ、年初来の利益を全て失ったという。
損失が一定の水準に達すると、資産を売却したりすることが多いようだ。
足元の相場混乱で、アイスラーのように大規模な損失、最悪の場合はファンドの清算に迫られるところも出てくるのではないか。
市場は疑心暗鬼に陥っている。
相場急変動に伴う「清算」の影響は今週以降も出てくるかもしれない。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ツナグHD(6551)・・・動兆
小売業・飲食業のアルバイト採用代行が主力。
採用広告の最適化、倉庫などへの人材派遣も
(兜町カタリスト櫻井)
15日の東京株式市場はは、堅調な展開か。
日経平均株価予想レンジは、3万3800円-3万4400円を想定。(14日終値3万3982円36銭)
米国株は上昇。ダウ平均は312ドル高の40524ドルで取引を終えた。
現地14日の米国株式が続伸した動きを受けて、買い優勢スタートが見込まれる。ただ、半導体関連に関する米相互関税の行方が不透明なことから、関連銘柄には手控えムード広がる場面もありそう。為替相場は、ドル・円が1ドル=143円前後(14日は143円06-08銭)と小動きの一方、ユーロ・円が1ユーロ=162円台の前半(同162円94-98銭)とやや円高方向にあるシカゴ日経平均先物の円建て清算値は、14日の大阪取引所清算値比125円高の3万4295円だった。
【好材料銘柄】
■VRAIN Solution <135A>
今期経常は54%増で4期連続最高益更新へ。
■ジェイフロンティア <2934>
今期経常を一転黒字に上方修正。
■ドトール・日レスホールディングス <3087>
今期経常は12%増で9期ぶり最高益、前期配当を2円増額・今期は4円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.98%にあたる350万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から10月14日まで。
■ラクト・ジャパン <3139>
12-2月期(1Q)経常は43%増益で着地。
■プロパスト <3236>
今期経常を一転5%増益に上方修正。
■フライヤー <323A>
今期経常は50倍増で2期連続最高益更新へ。
■ビーロット <3452>
今期経常を一転8%増益に上方修正・最高益、未定だった配当は9円増配。
■THE WHY HOW DO COMPANY <3823>
非開示だった今期経常は黒字浮上へ。また、マゼックスと業務提携。
■テラスカイ <3915>
今期経常は23%増で2期連続最高益更新へ。
■エコモット <3987>
上期経常は2.9倍増益・通期計画を超過。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.85%にあたる15万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から8月31日まで。
■日本特殊塗料 <4619>
シティインデックスイレブンスが14日付で大量保有報告書を提出。シティインデックスイレブンスと共同保有者の日特塗株式保有比率は5.06%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
■property technologies <5527>
12-2月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。
■ABEJA <5574>
今期経常を一転30%増益に上方修正。
■SMN <6185>
前期最終を93%上方修正。
■TWOSTONE&Sons <7352>
上期経常が12倍増益で着地・12-2月期も87倍増益。また、戦略コンサルティングサービスを手掛けるSAICOOLの株式を取得し子会社化する。
■バリュークリエーション <9238>
今期経常は50%増で2期ぶり最高益、0.5円増配へ。また、株主優待制度を拡充。26年2月末基準日から優待品をデジタルギフトに変更し、保有株数と保有期間に応じて3000~1万2000円分を贈呈する。従来はQUOカード1500~6000円分を贈呈していた。実質倍増。そのほか、1億円のビットコインを追加購入。
■ラストワンマイル <9252>
上期最終が2.4倍増益で着地・12-2月期も2.7倍増益。
【主な経済指標・スケジュール】
15(火)
【国内】
20年国債入札
《決算発表》
日置電、ボードルア、大研医器、三機S、メタリアル、きょくと、JMACS
【海外】
独4月ZEW景況感指数(18:00)
米4月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
米3月輸出物価指数(21:30)
米3月輸入物価指数(21:30)
《米決算発表》
ジョンソン&ジョンソン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、PNCファイナンシャル
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります
14日のNYダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比312ドル08セント(0.77%)高の4万0524ドル79セントで終えた。
トランプ米政権が11日、相互関税の対象から電子関連製品を除外した。関税引き上げを巡る過度な警戒が後退し、投資家のリスク回避姿勢が和らいだ。ダウ平均の上げ幅は500ドルを超える場面があった。
米政権は11日夜、事業者向けの通知で、スマホやパソコン、半導体製造装置などを相互関税の対象から除外することを明らかにした。中国で多くの製品を生産する大手ハイテク企業に朗報となり、アップルなどに買い戻しが入った。
ただ、トランプ大統領は13日にはSNSで、スマホやパソコンを関税対象から除外しない考えを表明。同日夜には記者団に対し、半導体への追加関税を「来週にも公表する」などと説明した。高関税政策を巡る先行き不透明感は払拭されておらず、投資家らは慎重姿勢を崩していない。
トランプ米大統領が14日、「いくつかの自動車企業に対して何か助けることを考えている」と話したと伝わった。米国での生産に切り替えるために「少々時間が必要だ」との認識を示したという。ダウ平均の構成銘柄ではないが、フォード・モーターやゼネラル・モーターズ(GM)などが買われた。前週には一部の国・地域を対象に相互関税が90日間停止された後で、貿易摩擦の激化を巡る過度な懸念が後退した。
市場では「最悪なシナリオを織り込んできた後でポジティブな材料に対して反応しやすい」との声が聞かれた。米債券市場では長期金利の上昇(債券価格の下落)が一服した。14日は前週末終値(4.49%)を下回って推移し、4.36%をつける場面があった。長期金利の低下も、投資家心理の一定の支えになった。
米連邦準備理事会(FRB)のウォラー理事は14日の講演で、関税引き上げによるインフレは「一時的」との見方を示した。「景気減速が著しく、景気後退の危険までさらすようであれば、私が従来考えていたよりも早く、より大幅に政策金利を下げることを支持するだろう」とも話した。FRBが必要に応じて利下げに動くとの見方も、株買いの安心感につながった。
ただ、ダウ平均は小幅安に転じる場面もあった。ラトニック米商務長官は13日の米ABCニュースの番組で、11日に除外した製品を今後詳細が発表される「半導体関税」に組み入れると表明した。米政権の通商政策の不透明感がなお強いことは、米株相場の重荷となった。
ダウ平均の構成銘柄では14日発表の2025年1〜3月期決算で1株利益などが市場予想を上回ったゴールドマン・サックスが買われた。アムジェンやトラベラーズ、ウォルマートも高い。半面、ユナイテッドヘルス・グループやアマゾン・ドット・コムは売られた。今後4年間で最大5000億ドル相当の人工知能(AI)インフラを米国で生産する計画を発表したエヌビディアは小幅に下げて終えた。
ナスダック総合株価指数は続伸した。前週末比107.028ポイント(0.63%)高の1万6831.484(速報値)で終えた。アルファベットやパランティア・テクノロジーズが買われた。
 【シカゴ日本株先物概況】
【シカゴ日本株先物概況】
14日のシカゴ日経平均先物は上昇した。6月物は前週末比645円高の3万4295円で終えた。この日はトランプ米政権が相互関税の対象から一部製品を除外したのを受けて日米で株式相場が上昇し、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
34295 ( +125 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
34410 ( +240 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
14日の英FTSE100種総合株価指数は3日続伸し、前週末比170.16ポイント(2.13%)高の8134.34で終えた。トランプ米政権が11日、相互関税の対象からスマートフォンなど電子関連製品を除外した。分野別関税の対象になるとされるものの、市場の警戒感がひとまず和らいだ。
英HSBCホールディングスやバークレイズなど銀行が上昇したほか、英BPといったエネルギーも買われた。航空機エンジン大手ロールス・ロイス・ホールディングスをはじめとする資本財やヘルスケア関連、資源、消費関連と幅広い業種・銘柄に買いが広がった。FTSE100種指数を構成する銘柄のうち、英ロンドン証券取引所グループ(LSEG)を除く99銘柄が上昇した。
FTSEの構成銘柄では、投資会社メルローズ・インダストリーズが5.53%高、保険会社セント・ジェームズ・プレイスが4.93%高、金融大手スタンダード・チャータードが4.92%高と相場をけん引。一方、ロンドン証券取引所は0.81%安と唯一下げた。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
14日のドイツ株価指数(DAX)は反発し、前週末比580.73ポイント(2.85%)高の2万0954.83で終えた。トランプ米政権が、スマートフォンなど電子関連製品を相互関税の対象から除外する措置を決めたことを受け、米関税政策を巡る投資家の警戒感がやや和らいだ。前週末に上昇した米株式相場が14日に続伸して始まったのも、投資家心理を支えた。
DAXは4月に入って以降、水準を大きく切り下げているため、値ごろ感からの買いも入りやすかった。
個別では、防衛大手ラインメタルが5.84%高、エネルギー大手シーメンス・エナジーが5.81%高、ドイツ銀行が5.23%高と大きく買われた半面、日用品大手ヘンケルのみが0.72%安とマイナス圏で引けた。
■フランス・パリ株価指数
フランスの株価指数CAC40は反発し、前週末比2.36%高で終えた。


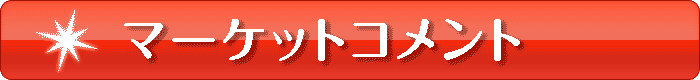
 前日の米株式市場では、NYダウは312ドル高と上昇した。トランプ米政権がスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税の対象から一時除外したことを好感する買いが流入した。これを受け、東京株式市場も日経平均株価は上昇してスタートし、午前9時30分過ぎには400円を超える値上がりとなる場面があった。トランプ米大統領が14日、「一部の自動車メーカーを助ける何らかの方策を検討している」と語ったと伝わり、自動車関税の救済策への期待が高まり自動車株が買われた。米株式市場でフォード・モーターなど自動車株が上昇した流れを受け、東京株式市場でもトヨタやホンダ、SUBARU、デンソーなど自動車や部品銘柄に買いが集まった。東証の業種別騰落率ランキングで輸送用機器は値上がり率首位となった。
前日の米株式市場では、NYダウは312ドル高と上昇した。トランプ米政権がスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税の対象から一時除外したことを好感する買いが流入した。これを受け、東京株式市場も日経平均株価は上昇してスタートし、午前9時30分過ぎには400円を超える値上がりとなる場面があった。トランプ米大統領が14日、「一部の自動車メーカーを助ける何らかの方策を検討している」と語ったと伝わり、自動車関税の救済策への期待が高まり自動車株が買われた。米株式市場でフォード・モーターなど自動車株が上昇した流れを受け、東京株式市場でもトヨタやホンダ、SUBARU、デンソーなど自動車や部品銘柄に買いが集まった。東証の業種別騰落率ランキングで輸送用機器は値上がり率首位となった。

 【シカゴ日本株先物概況】
【シカゴ日本株先物概況】